安倍晴明の伝説(『葛葉物語』による安倍晴明の物語)
2016/02/03
陰陽師・安倍晴明の経歴は史実上不明点が多く、若かりし頃の経歴は主に伝説として語られています。
また、晴明の生誕から出仕について語った伝説は多数あり、その内容もそれぞれによって多少異なります。
そこで、今回は『葛葉物語』による安倍晴明の物語を紹介したいと思います。
安倍晴明についてはこちらの記事を参照:【安倍晴明とは?】
第一章
阿倍保名
昔、摂津国の阿倍野という所に、阿倍保名(あべのやすな)という侍が住んでいました。
この保名の遠い先祖には阿倍仲麻呂(あべのなかまろ)という名高い学者がおり、唐に渡っても唐の学者たちに引けを取らないほど優秀な人物でした。そこで、唐の皇帝は仲麻呂を日本へ還えすことを惜しみ、無理やり唐に引き止めました。
そのため、仲麻呂は帰国することなく唐で暮らし、その生涯を終えました。
仲麻呂の死後、日本に残された子孫も代々 田舎に埋もれていき、とうとう田舎侍になってしまいました。また、仲麻呂の代から伝わる天文や数学の難しい書物は家に残っていましたが、誰も読む者が居なかったため、何百年間も古い箱の中にしまい込まれたままになっていました。
保名はそれを残念に思い、先祖の仲麻呂のような学者になって阿倍家を再興したいと思いましたが、子供の時から馬に乗ったり弓を射たりすることは得意でも学問はさっぱりでしたので、せめて立派な子供を生んで、その子を先祖に負けないくらいに偉い学者にしようと思い立ちました。
そこで、隣の和泉国の信田明神に月詣りをして、立派な子供を授かるよう熱心に祈願しました。
信田の牝狐
ある年の秋の半ばのこと、保名は5、6人の家来を連れて信田明神に出かけ、いつも通りに祈願を済ませた後、しばらく休憩しようと幕を張り、萩やススキの咲き乱れる美しい景色を眺めながら 家来達と酒盛を始めました。
そのうち日が暮れて暗くなってきたので、保名達が帰り支度を始めると、向こうの森の奥で大勢が騒ぐ声が聞こえました。その中には太鼓や法螺貝の音も交っており、まるで戦のような大騒ぎでした。
そして、だんだんとこちらの方に近付いて来たので、保名達は幕の中で身構えて待っていると、近くの草むらから悲しそうに鳴く狐の声が聞こえ、直に一匹の若い牝狐が保名達の幕の中に飛び込こんで来きました。
その狐は保名の足元まで来ると、首をうなだれたまま尻尾を振り、悲しそうな声で鳴きました。保名は この狐が誰かに追われて逃げ場を失なっていることに気付き、哀れに思って家来に担がせた箱の中に入れて匿うことにしました。
すると間もなく、喧しい声と共に何十人もの侍が森の中から駆け出して来て、いきなり保名達の幕の中に飛び込んで辺りを探し始めました。
この乱暴に腹を立てた保名は、その侍達に「貴方達は誰なのですか、何の断わりもなく人の幕の中に入って来るとは、乱暴ではありませんか」と咎めると、その中の頭が「生意気を言うな、我々が見つけた狐が この幕の中に逃げ込んだから探しているのだ。さっさと狐を出せ」と言い返しました。
それからだんだんと激しい口論となり、それに逆上した侍達はやがて刀を抜いて斬りかかって来ました。しかし、保名も家来達も皆強い侍でしたので、刀を抜いて応戦し、とうとう侍達を追い詰めて 残らず追い払ってしまいました。
そして、箱の中に匿った狐を出してやりました。すると、狐は まるで人間が手を合わせて拝むような格好で何度も拝み、嬉しそうに尻尾を振って、草むらの中に去って行きました。
狐の姿が見えなくなると、森の向こうで さっきの何倍も騒がしい声がしました。その声に驚いて振り返ると、すぐ目の前に立派な馬に乗った大将らしき侍が立っており、今度は何百人という侍が一塊になって 保名達をあっという間に取り囲みました。
そこで再び激しい戦が始まり、保名達は必死に応戦したものの、多すぎる敵に全く歯が立たず、保名の家来達は残ず討ち取られてしまい、保名も体中に矢傷や刀傷を負った上、手足を押さえられて捕まってしまいました。
石川悪右衛門
この馬に乗った大将は、隣の河内国に住む石川悪右衛門(いしかわあくうえもん)という侍でした。そして、その兄の芦屋道満(あしやどうまん)は、帝(みかど)に仕えて天文や占いを行っており、その実力は日本一と言われるほど評判の高い学者でした。
また、悪右衛門の妻は重い病に罹っており、医者に診せても少しもよくならなかったので、兄の道満に頼んで占ってもらったところ、「妻の病気は普通の薬で治るものではない、治すには若い牝狐の生き肝を取って煎じて飲ませるより他にない」という結果がでました。
そこで悪右衛門は、大勢の家来を連れて信田の森に狐狩りにやって来ました。しかし、一日中 森の中を駆かけ回っても全く獲物が見つからなかったため、すっかり癇癪を起こして腹立たしく引き上げようとしたところ、長いススキの陰に隠れている親子三匹の狐が見つけました。
大喜びで早速 捕らえようとすると、親子の狐は驚いて親狐は共にさっさと逃げてしまいましたが、若い小狐が逃げ場を失い、大勢に追われながら、やっとの思いで保名の幕の中に逃げ込んだのでした。
悪右衛門は、苦労して手に入れかけた狐を保名に逃がされてしまったことから、憎しみにまかせて 捕らえた保名を殺そうすると、向こうから「しばし待たれよ」と声を掛けられました。
藤井寺の和尚
悪右衛門が振り返ると、声を掛けたのは河内国の藤井寺の和尚でした。この寺は石川家代々の菩提所だったので、悪右衛門と和尚は普段から親しい間柄でした。
そこで、和尚が悪右衛門に保名を殺そうとする理由と尋ねると、悪右衛門は狐狩を保名に邪魔をされたという一件を話し、そのことが悔しくて保名を殺そうとしていると述べました。
すると、和尚は静かにに話を聞いた後で「なるほど、それで腹の立つのはごもっともです。しかし、人の命を取るというのは容易なことではありません。大切な奥方の命を助けようとしている時に他人の命を取るというのは、仏様の思し召しにも適わないでしょう。他人の命を取ったところで奥方が助かるわけでもありますまい」と言いました。
こう和尚に諭されると、さすがに傲慢な悪右衛門でも心が挫け、和尚はここぞと「しかし、ただ助けるというのが気に食わないのでしたら、こうしましょう。この男を今日から私の弟子として出家させます。それで堪忍しておやりなさい」と言いました。
悪右衛門もとうとう和尚に説き伏せられて、保名を放してやることにしました。そして、悪右衛門は和尚に別れを告げて、森の中に去って行きました。
悪右衛門の姿が見えなくなると、和尚はうなだれていた保名に向って「私は先ほど貴方に助けて頂いた狐です。御恩は一生忘れません。さあ、乱暴者は去って行きました。また見つからないうちに、向こうの道からそっとお逃げください。」と言い、元の狐の姿に戻って、悪右衛門達とは別の方角の道に入っていきました。
また、保名に向かって尻尾を振る姿は、さも自分について来いと言っているように見えました。保名は夢の中で夢を見たような心持ちで、ぼんやりと狐の後を追って行きました。
第二章
葛の葉
保名が狐を追っていくうち、すっかり日が暮れて夜になり、暗い樹の間から吹けば飛ぶように薄い三日月がきらきらと光って見えていました。また、いつの間にか狐の行方を見失しなってしまい、心細く森の中を進んで行きました。
そして、しばらく進むと やがて森を抜け、谷間のような所に出ました。保名は体中に受けた傷が痛みと共に疲れも溜まっていたので、喉が渇いててたまりませんでした。
そこで、水辺を探して谷へと下っていくと、遥か谷底に一筋の白い布を延べたような清水を見つけました。そのとき、月の光が仄かに当たり、その中に微かに人影が見えたので、保名は安心して岩角を辿って下って行くと、そこには着物を洗う16、7歳の可愛らしい少女がいました。
保名が足を引きずりながら少女に近づいていくと、少女は叫び声を上げるほど驚き、危うく岩を踏み外しそうなりましたが、保名は「私は怪しい者ではありません。大勢の悪者に追われて怪我をしているのです。どうか水を一杯飲ませて下さい。」と言いました。
少女は気の毒に思い、谷川の水を汲んで保名に飲ませてやりました。そして、傷付いた保名を見つめて「そんな痛々しい様子では途中で倒れてしまうでしょう。よろしければ私の家で傷の手当をなさってください」と言いました。
保名は喜んで少女の跡について行き、山陰の寂しい所にある少女の家へとやってきました。しかし、その家には少女の他に誰も人は居なかったので、保名がそれを尋ねると、少女は葛の葉(くずのは)という名であり、親兄弟も無く一人でここに住んでいるというのでした。
そして、保名が一晩休んで目覚めると、傷を受けたところが酷く腫れ、体中が搾木(しめぎ)にかけられたように痛んで、立つことも座ることもできませんでした。そのため 保名はしばらく寝たきりの日々を過ごし、その間は親切な葛の葉の世話になっていました。
保名の身体が治るまでには時間がかかりましたが、葛の葉は毎日 少しも飽きずに保名を介抱し、まるで親兄弟を世話するかのように親切にしました。そして、保名の立てるようになった頃には とうとう冬の半ばになっていました。
阿倍童子
山の冬は厳しく、やがて積もった雪が森や谷を埋めるように覆い尽くしたため、保名は冬の間 森を出ることができませんでした。しかし、春が近付くと だんだん雪が解け始め、森の中では時々 小鳥のさえずりも聞こえるようになりました。
保名は葛の葉と毎日を過ごすうち、だんだん自分の家のことを忘れるようになり、さらに一年が過ぎて 二度の春が訪れた頃には、二人の間に可愛らしい男の子が一人生まれたので、阿倍童子(あべのどうじ)と名付けました。
この頃、保名はすっかり侍の身分を忘れて、朝早くから日が暮れるまで、家の裏の小さな畑で百姓仕事をし、葛の葉は童子の世話をする合間に機に向かって、夫や子供の着物を織って過ごしました。
そして、夕方になると 保名が畑で採れた野菜や、仕事の合間に森で捕まえた小鳥をぶら下げて帰って来て、葛の葉は童子を抱いて夫を迎えるという仲睦まじい幸せな日々を送りました。
こうして平和な日々を送っている内に、童子の年は7歳になりました。
狐になった葛の葉
ある秋の日、保名はいつも通りに畑に出て、子供も野山に遊びに出掛けたまま帰って来なかったので、葛の葉は一人寂しく留守居をしていました。そして、葛の葉もいつも通りに機に向かって着物を織っていましたが、少し疲れたので手を止めて、庭を眺めて休憩しました。
すると、もう薄れかけた秋の夕日の中に、白い菊の花が仄かな香を立てていました。そのとき、葛の葉は急に寂しい気分になって、我を忘れて呆然としていました。
しばらくすると、外から母を呼ぶ声が聞こえ、やがて遊び疲れた童子が帰って来きましたが、呆然とした葛の葉の耳には童子の声が届きませんでした。童子は返事が無いのを不思議に思い、そっと庭に入ってみると、機に向っている母の姿が転寝をしているのが見えました。
しかし、そこで見た母の顔は人間ではなく 狐の顔になっていたので童子は驚いてしまいました。童子は さすがに見間違いだと思ながら再び顔を覗いてみると、それは紛れもなく狐の顔でした。そこで童子は思わず叫び声を上げ、後ろを振り向くこともなく外へと駆け出して行きました。
童子の叫び声に目を覚ました葛の葉は、転寝をしている間に自分の顔が狐に戻っていることに気付き、それを子の童子に見られてしまったことを悟りました。そして、自分が保名に救われた若い牝狐だったということを思い出し、また自分の醜い正体を童子に見られてしまったことを恥じて、とても悲しくなりました。
そして、もうこの生活を続けられないと涙をこぼし、部屋の障子に「恋しくば 尋ね来て見よ 和泉なる 信田の森の うらみ葛の葉」という歌を残して、保名と童子を名残惜しんで何処に消え去ってしまいました。
金の箱と白い玉
日が暮れて 保名が家に帰ろうとすると、童子が鳴きながら保名のもとにやって来て、先ほど見た母の姿を保名に話しました。すると、保名は驚いて、童子と共に慌てて家に帰ってみると、いつもなら聞こえるはずの機の音が無く、ひっそりと静まり返っていました。
また、葛の葉の姿が見当たらなかったので、家中を探し回ってみましたが葛の葉の姿はどこにもありませんでした。そして、夕暮れの薄明りの中に、障子に白く浮き出した葛の葉の歌を見つけました。
自分のせいで母が居なくなったと思った童子は酷く後悔し、暗くなるまで母を探し歩きましたが、結局 見つけることができず、母恋しさにしばらく泣いていました。あんまり童子が泣くので、困った保名は童子の手を引いて、当てもなく真っ暗の森の中を方々探し歩きました。
その間、葛の葉は元の住処である信田の森までやってきて、二人の前に二度と姿を現すまいと堅く心に誓っていましたが、夜中になって、保名が自分を探す声と共に、童子の泣き声が聞こえてきたため、それに心が挫けて 草むらの中に姿を現してしまいました。
すると、童子は喜び 慌てて取り縋ろうとしましたが、そのときの葛の葉は人間では無く、狐の姿に戻っており、「私に触れてはなりません。一旦 元の住処に帰れば人間との縁は切れて無くなってしまうのです」と言いました。
そこで保名は「お前が狐であろうと構わない、童子のためにも せめてこの子が10歳になるまで一緒に居てくれないか」と言いましたが、葛の葉は「10歳までと言わず、一生でも童子の傍に居たいのですが、私はもう二度と人間の世界に帰ることのできない身になりました。ここに形見を残しておきますから、いつまでも私を忘れないで下さい」と言いました。
そして、一寸四方ほどの「金の箱」と、水晶のような透き通った「白い玉」を保名に渡し「この箱の中に入っているのは『竜宮の不思議な護符』です。これを持っていれば、天地はもとより人間界のあらゆる出来事を目で見るように知ることができます。また、この『白い玉』を耳に当てれば、鳥獣をはじめ草木や石ころの言葉でさえも、手に取るように分かるようになります。この二つ宝物を童子に与えて、日本一の賢人に育ててやってください」と言い残して、葛の葉は再び信田の森に戻って行きました。
第三章
狐の子
狐の子である阿倍童子は生まれつき大そう賢く、狐の宝物を授かったせいか、8歳になる頃には大人でも難しい本を読みはじめ、阿倍家に代々伝っている天文、数学の巻物から、占いや医学の本まで、あらゆる書物を読んで学び、13歳になる頃には日本で右に出る者が居ないほどの学者になるほど成長していました。
ある日、童子がいつも通りに天文の本を読んでいると、庭の柿の木に二羽の烏(カラス)が飛んで来て、会話をするかのように騒がしく鳴いていました。そこで、童子は白い玉を取り出して 烏の鳴き声に耳を傾けると、一羽の烏は東からやってきた関東の烏で、もう一羽の烏は西からやってきた京都の烏だと分かりました。
そして、京都の烏が「都の御所では帝が大病を患って大騒ぎになっているぞ。医者や行者を集めて療治や祈祷しているが、一向良くならない。それもそのはず、あれは病気ではないのだよ」と言うと、関東の烏が「一体どういう理由なんだね」と尋ねました。
すると京都の烏が「それはこういう理由さ。最近 御所の建替したんだが、帝の御殿の東北(うしとら)の柱を立てた時、その下に蛇と蛙を生き埋めにしてしまったのさ。それが土台石の下で今でも生きていて、夜も昼もなく睨み合って争っている。蛇と蛙が怒って吹き出す息が炎となって空まで立ち昇ると、今度は天が乱れる。その勢いで帝は体を病んでしまっているのさ。だから、あの蛇と蛙を追い出してしまわないうちは帝の病は治るわけないんだよ」と説明しました。
それを聞いた関東の烏は「なるほど、それは人間になんて分かるわけ無いな」と言うと、二羽で顔を合わせて嘲るようにカアカアと笑いました。そして、二羽は互いの住処を目指して、別れて飛んでいってしまいました。
烏の会話を聞いた童子が早速 占ってみたところ、烏の言う通りの結果が出たので、保名にこのことを話して「どうか、私を京都に連れて行って下さい。帝の病気を治してあげとうございます」と言いました。保名も阿倍家を再興する好機と大変喜んで、童子を連れて京都に上りました。
安倍晴明
京都に着いた二人は早速 御所を訪れて、帝に事の次第を申し上げました。すると、帝も保名が阿倍仲麻呂の子孫だというで喜んで、保名親子の願いを聞き入れることにしました。
そして、童子は御所の東北の柱のことを役人たちに話して、掘り返してみるように頼みました。最初は役人達も不思議がって童子の頼みを聞き入れませんでしたが、何もしないことで帝の病が治るわけでもないので、物は試しにと 東北の柱の下を掘り返してみると、童子の言う通りに 火のように荒い息を吐いて争っている蛇と蛙を見つけました。
そこで、その蛇と蛙を追い出してまもなくすると、帝の病気もだんだん良くなって行きました。
帝は童子の手柄を褒め称え、その月がちょうど三月の清明(せいめい)の季節だったことから、童子に阿倍清明(あべのせいめい)いう名を与えて、従五位の位を授け、陰陽頭(おんみょうのかみ)という役職に任じました。
その後、清明は「清」の字を「晴」に変えて「阿倍晴明」と名乗るようになり、人々から「占いの名人(陰陽師)」として評判を集めるようになりました。
第四章
芦屋道満
たった13歳の阿倍童子が、帝の病気を治して偉い役職に就いたと聞いて 一番悔しがったのは、あの石川悪右衛門の兄の芦屋道満でした。道満は晴明が現れるまでは日本一の学者という名声を欲しいままにしており、天文と占いの名人と評判でしたが、帝の病を治すという大手柄を子供に取られてしまったので、悔しがるのも無理はありません。
そこで道満は、御所に上がって帝に「あの童子は詐欺師でございます。恐れながら、陛下の病は侍医の方々や、私どもの丹誠でそろそろ治る時が近づいていました。そこに あの童子が時期を見図って現れ、横合から手柄を奪っていったのでございます。御所の柱の蛇と蛙の不思議も、あれら親子が御所の役人を誑かして、わざわざ入れて置いたものかも知しれません。どうかご注意ください」という風に讒言しました。
また、続けて「一度 私と法術比べをさせて頂きとうございます。もしあの童子が負ましたならば、それこそ詐欺師の証拠でございます。その暁には早速 童子の位を取り上げて、追い返して頂きとうございます」と申し上げました。
すると、帝は「ならば、お前がもし童子に負けたらどうするのだ」と少々怒りながら尋ねると、道満は「はい、万一 私が負けるようなことがございましたら、それこそ私の頂いたお役目も位も残らずお返し申し上げ、私は童子の弟子になって、修業をいたしましょう」と、高慢な顔をしながら申し上げました。
晴明と道満の対決
帝は早速 阿倍親子を呼び出して、御前で術比べさせることを伝えました。そして、道満と晴明を右左に別れて着席させると、やがて4、5人の役人が重く大きな長持を担いで来て、二人の前に据えました。
そこで、役人の頭が「道満、晴明、この長持の中には何が入っているか当ててみよ、と陛下が仰せです」と言うと、道満は得意げな顔をして「晴明、まずはお前が答えよ。先を譲ってやる。」と言いました。
晴明は道満に丁寧に頭を下げて、「では失礼ですが、私から申し上げましょう。この長持の中に入っているのは猫二匹です」と答えました。道満は晴明が上手く言い当てたことに驚きながらも「きっと、まぐれ当たりに違いないが、二匹の猫に相違ありません。しかし、二匹のうち一匹は赤猫、もう一匹は白猫でございます」と答えました。
そして、長持の蓋を開けると、赤白二匹の猫が飛び出してきました。これには、帝も役人達も舌を巻いて驚きましたが、互いに当ててしまっているため、もうひと勝負することになりました。
今度は厚い布を被せた大三方(神饌を乗せる台)が運ばれてきたので、道満はそれを見るなり「では私から申し上げましょう。三方の上にある品は蜜柑(みかん)15個です」と答えました。晴明はその様子を見て、少し悪戯して、高慢な道満の鼻を明かしてやろうと思い、術を使って三方の上の品を素早く入れ替え「これは蜜柑15個ではございません。鼠(ねずみ)15匹でございます」と答えました。
三方に乗せたものを知っている帝や役人たちは驚いて、今度こそ晴明がしくじったと思いました。また、その様子を見た父の保名も真っ青になって息子の袖を引きましたが、晴明本人はあくまで平気な顔をしていました。一方、道満は真っ赤になって「さあ、詐欺師が証拠を現しましたぞ。さあ、早く開けなさい、早く」と叫びました。
そして、役人が三方の覆いを取ると、三方の上から15匹の鼠が飛び出だしてきて、御殿の床を駆かけ歩きました。すると長持の上で寝ていた二匹の猫が いきなり飛び下りて、鼠を追い回しました。その光景を見た皆は総立ちになって、やがて御殿中で大騒ぎになりました。
これで勝負が着いたので、道満は約束通りに位を取り上げられ、阿倍晴明の弟子になりました。
参考サイト:『日本の諸国物語(葛の葉狐)』(青空文庫)
スポンサーリンク

「日本神話」を研究しながら日本全国を旅しています。旅先で発見した文化や歴史にまつわる情報をブログ記事まとめて紹介していきたいと思っています。少しでも読者の方々の参考になれば幸いです。
スポンサーリンク
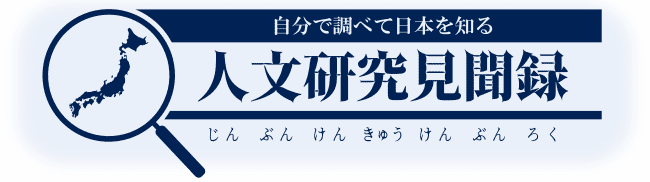

コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿